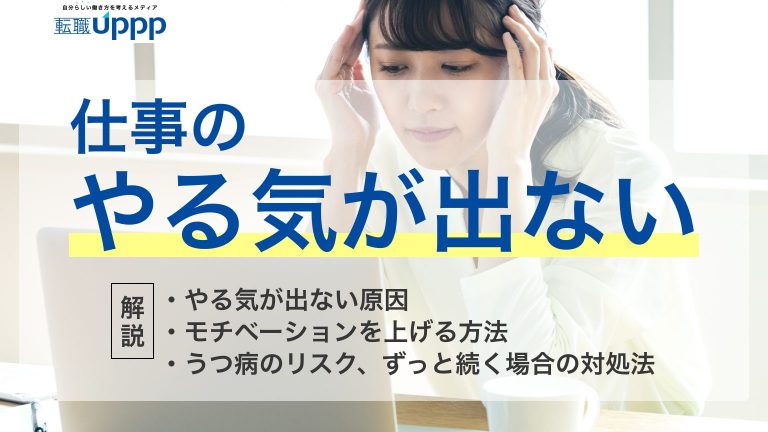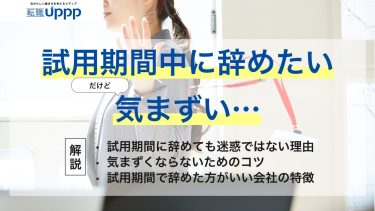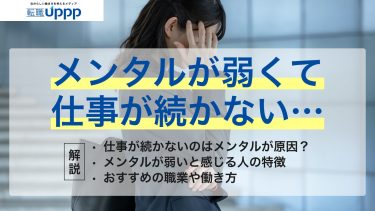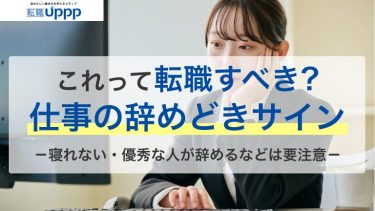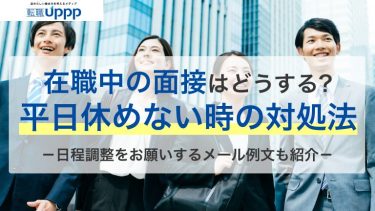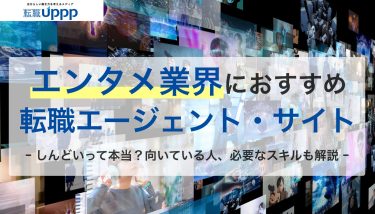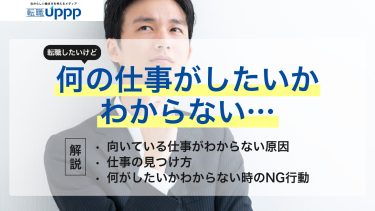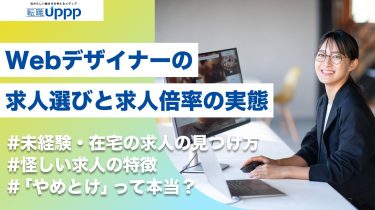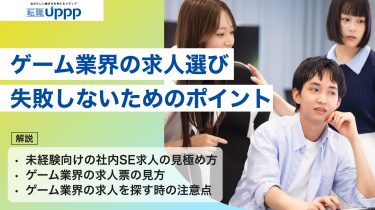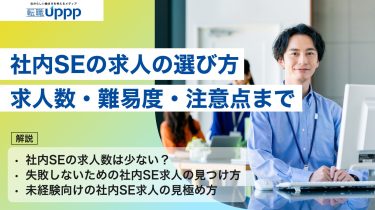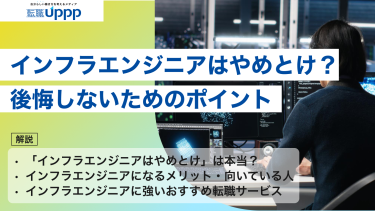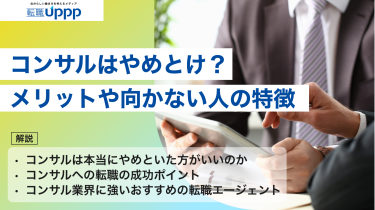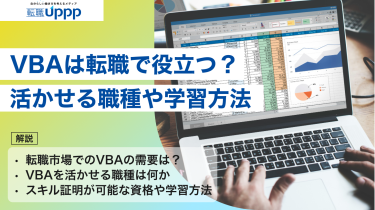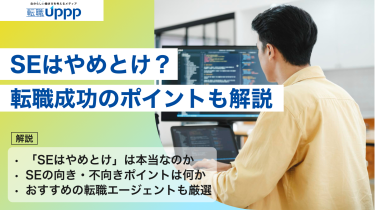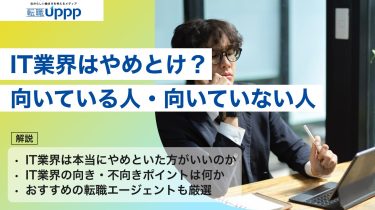「最近、なんだか仕事に気が乗らない」「頑張らなきゃと思っても体が動かない」このように感じていませんか?
一時的な気分の波かもしれませんが、もしかしたら、もっと深い理由が隠れているかもしれません。
この記事では、仕事にやる気が出ない原因を主な7つに分けてわかりやすく解説し、年代別の傾向や今すぐできる対処法、気をつけたいNG行動まで詳しく紹介します。
さらに、やる気の低下が長く続く場合に考えられる病気の可能性や、そのときに取るべき行動についてもお伝えします。
「自分だけじゃなかった」とホッとしたり、「これならできそう」と思えるヒントがきっと見つかるはずです。
大学卒業後、国内金融機関を皮切りに、グローバルコングロマリット企業や外資系IT企業等において、戦略子会社の立上げ、事業清算、買収合併による、3度の組織統廃合 等を経験。
小規模同士の合弁など、早期統合効果を狙う際の計画策定、実行の支援にも強みを持つコンサルティングと並行して、キャリアカウンセラー、非常勤講師として活動中。
資格
- 日本経団連認定キャリアアドバイザー(番号:NCAー004ー020)
- 産業カウンセラー(番号:14005503)
仕事でやる気が出ないのはなぜ?モチベーションが下がる原因7つ
仕事に対してやる気が出ないと感じるのには何らかの理由があります。
ここでは、多くの人が抱えやすい代表的な原因を7つに分けて紹介。自分に当てはまるものがあるか、まずはチェックしてみてください。
- 仕事で心身ともに疲れている
- 社内の人間関係が悪い
- 仕事にやりがいを感じていない(ルーティンワークになっている)
- 企業の風土や事業戦略に共感できていない
- 給与などの待遇がよくない
- 仕事が正当に評価されていないと感じる
- 今の仕事がキ自信のャリア形成につながらないと感じている
原因1:仕事で心身ともに疲れている
仕事にやる気が出ない一番の理由は、心や体が疲れていることが考えられます。
マイナビ転職のアンケート調査でも、やる気が出ない時は「心や体が疲れている時」と回答する人が最も多かったと報告されています。※1
人間の脳は強いストレスや疲労状態が続くと、判断力や集中力、感情のコントロールに関わる前頭前野の働きが鈍くなることがわかっています。
前頭前野の機能低下は、モチベーションの源とされる「意欲の発火点」にも影響を与えるため、当然ながら仕事へのやる気も低下します。※2
さらに、厚生労働省の報告によれば、長時間の労働は精神的負担のリスク要因とされており、慢性的な疲労やストレスはメンタルヘルスにも悪影響を及ぼすと明記されています。※3
このように、やる気の低下は単なる「気の持ちよう」ではなく、心身に疲労サインが現れている兆しであることが多いのです。
まずは、自分の身体的・精神的コンディションを冷静に見直すことが、的確な対処の第一歩となります。
原因2:社内の人間関係が悪い
多くの方は経験があるかと思いますが、職場の人間関係が悪いとき、やはり仕事のやる気は確実に下がってしまいます。これは感情の問題、実際にデータで裏づけられた深刻な課題です。
厚生労働省が実施した「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、調査対象の29.6%の人が、職場でストレスを感じる原因は「対人関係」と回答し、ワースト3に入っています。
人間関係がこじれている、あるいは、コミュニケーションがうまく取れない職場では、お互いの報告・連絡・相談が滞り、結果的にミスやすれ違いによってストレスが溜まりやすくなります。
さらに、相談や提案すら気を使うようになれば職場の雰囲気が悪くなり、安心して働ける環境は失われてしまいます。
こうした職場環境では、自分の意見や提案を出すことに強い不安を感じるようになり、やがて仕事への関心や意欲そのものが薄れていくというわけです。
原因3:仕事にやりがいを感じていない(ルーティンワークになっている)
自分の仕事にやりがいを感じられなくなると、どうしてもモチベーションはガクッと低下してしまいます。
特に毎日同じ作業を繰り返すようなルーティン性の仕事では、慣れた仕事であるため、自分の新しい工夫や判断が入る余地が少なく、仕事が単なる「作業」に感じられてしまいがちです。
そうすると、どうしても自分の仕事の成果に対して、充実感が感じられなくなりがちです。
どれだけ仕事を真面目にこなしても、達成感や成長の実感が得られない日々が続くと、「自分はこの仕事を通じて何を得ているのか」「このままでいいのか」と疑問が生まれてくることでしょう。
その状態が長引くと、仕事の意味が見出せなくなり、いつの日か「今日はもう適当にやっておこう」といった気持ちが芽生えるでしょう。
本来は頑張りたい気持ちがあったとしても、やりがいのない環境では、それを維持することが難しくなるというわけです。
やる気の低下は怠けているからではなく、仕事の中に「目標」や「意義」を感じられなくなっているサインかもしれません。
原因4:企業の風土や事業戦略に共感できていない
会社の風土や事業の方向性、所属部門の方針などに共感できないと、仕事へのやる気を維持することはできません。
たとえば、自分が大切にしている価値観と、会社の方針がかけ離れていると日々の仕事に「意味」を感じにくくなります。
一方的な利益優先のやり方に違和感を覚えたり、上層部の決定が現場の声を無視していると感じたりすると、「自分の仕事は何のためにあるのか」と考え始めてしまうこともあるでしょう。
また、企業文化が極端に競争的だったり、年功序列のような硬直した風土だったりすると、自分らしさを出すことが難しくなり「ただ所属しているだけ」の感覚になりやすくなります。
こうした環境では、働く目的や自己成長の実感を持ちづらく、仕事に対する関心そのものが薄れていきます。
やる気を持ち続けて働くには、仕事内容だけでなく、会社の目指すビジョンや価値観に納得できるかどうかも重要です。
原因5:給与などの待遇がよくない
給与や待遇に納得できないと働く意欲が保ちにくいので、やる気が出ないのは当然。下記の通り、給与という報酬はモチベーションアップに重要な要素です。
報酬が「能力をフルに発揮した結果を評価されて得たもの」と見なされた場合には、その報酬は自分の有能さを証明する情報となり、自分の意思でもっと動いてみようというモチベーションが強まります。
反面、どれだけ努力して成果を出しても、それが給料や評価に反映されなければ「なぜこんなに頑張っているのに報酬につながらないのか」という疑問が積もっていきます。
特に、周囲と比べて報酬が低かったり、昇給やボーナスの評価基準が不透明だったりすると、「頑張っても意味がない」と感じやすくなります。
さらに、給与だけでなく、休日制度や福利厚生なども含めた労働環境が整っていないと、心身の疲れもたまりやすくなり、モチベーションの低下に直結します。
待遇への不満は、お金の問題にとどまらず、「会社からどう扱われているか」という信頼感にも関わるため、納得感のない職場ではやる気を維持するのは難しくなっています。
原因6:仕事が正当に評価されていない
自分の仕事が正しく評価されていないと感じると努力する意味を感じにくくなるので、やる気が出なくなる原因の一つ。仕事の評価はモチベーションに影響を与えると、下記の論文でも報告されています。
仕事の価値評価は労働者のモチベーション や職務満足度(Kalleberg 1977)に影響を与えるので,仕事からの報いを考える上で重要な視点となる。
人は「自分を見てもらえている」「認めてもらえている」「期待されている」と感じることで、自分の存在や役割に意味を見出します。
一方で、どれだけ頑張っても、会社組織からの反応(リアクション)が返ってこなければ、その仕事に情熱を注ぐ理由を失いかねません。
評価は、給与や役職に反映されるだけでなく、声かけや感謝の言葉など、日々のコミュニケーションにも現れます。
仕事の成果に対してリアクションがないと、「誰も見ていないなら手を抜いても同じ」「結局、誰がやっても同じなんじゃないか」と疑問や不信感が募っていきます。
原因7:今の仕事が自身のキャリア形成につながらないと感じている
今の仕事が自分自身の将来につながらないと感じていると、目の前の業務に意味を見いだせなくなります。
「この経験は、自分のキャリアにどう役立つのか」「今の仕事を続けた先に、どんな成長やチャンスがあるのか」こうした問いに明確な答えが見えないまま日々を過ごしていると、次第に働くことそのものが目的化してしまい、(義務的に)やらされている感覚ばかりが積み重なっていきます。
たとえば、担当業務の内容や質、レベルが何年も変わらない、専門性が身につかない、異動や昇進のチャンスもない。そんな状況では、「いまの努力が未来にどうつながるのか」が見えず、仕事への前向きなエネルギーが湧いてこなくなるのは当然のことです。
キャリアに繋がる実感が持てない仕事では「このままでいいのか」という不安が増していくため、働き続けること自体が苦しくなってしまうのです。

ここでは、代表的な例をあげましたが、「ふっと思うことがある」「何度も経験したことがある」ことではないでしょうか?忙しく過ごしていると、いつしか自身の思考行動パターンが惰性になっていたり、周囲からの評価が必要以上に低く見えたり、モヤモヤに陥りがちになります。時には、リフレッシュしたり、自身の置かれている現在位置を見つめなおす、ことも大切ですね。
試用期間中に「この職場、自分には合わないかも」と感じたとき、頭をよぎるのが「辞めたいけど、言い出しにくい」「すぐ辞めたら周りにどう思われるだろう…」という不安や葛藤ではないでしょうか。ですが、試用期間は“お試し期間”として設けられて[…]
【年代別の割合】20代だけじゃない!30代・40代ほど仕事でやる気が出ない
仕事にやる気が出ないと感じているのは若い20代だけではなく、実は、年齢が上がるほど「やる気が出ない」と感じる人は増えることが明らかになっています。
「仕事のやる気が出ないことがある」と回答した割合
- 20代:75.0%
- 30代:77.2%
- 40代:80.9%
- 50代:82.0%
この結果から見えてくるのは、社会人としての経験やスキルが増えるにつれて、やる気の低下を感じる人も増えているということ。
年齢を重ねると、責任が重くなり、役割が増える一方で、希望するキャリアに進めなかったり、思い描いていた未来と現実のギャップに直面したりすることがあります。
また、体力や生活スタイルの変化もあり、「仕事に集中しきれない」「以前のように頑張れない」と感じる瞬間が多くなるのかもしれません。
裏を返せば、やる気が出ないという感覚が「よくあること」であり、年齢に関係なく誰にでも起こり得ること、と言えそうです。
やる気が出ない日があっても、それはあなたの怠惰などではなく、多くの人が同じような気持ちを経験しているのです。

若い世代から見ると、経験を積んだ将来もずっとこのような状態が続くのかと、悲観的になってしまうかもしれませんが、周囲を見て、うまく感情やモチベーションをコントロールしている、と見える方はいないでしょうか? そんな方は、どうやって自分自身をうまく対応させているのでしょうか?
仕事でやる気が出ないときの7つの対処法
誰にでも起こりうる、仕事にやる気が出ないなと感じるときには、決して無理に頑張ろうとせず原因に合った対処をすることが大切です。
ここでは、やや沈みがちな気持ちを立て直すための、気軽にできることから、本腰をいれて取り組めることまで、具体的な7つの方法を紹介します。
- 仕事の目的・役割を再認識する
- リフレッシュ・休息する時間をつくる
- 趣味を見つけて没頭する
- ランニングやウォーキングなどの運動をする
- 直属の上司に相談する
- 新しいスキルを習得する
- キャリアプランを明確にして目標を立てる
対処法1:仕事の目的・役割を再認識する
仕事のやる気が出ないときは、「自分がこの仕事で何を任されていて〈期待されて)、なぜそれをやっているのか」を見直すことが効果的です。
毎日同じような作業やプロセスを繰り返していると、つい目の前のタスクを「こなすこと」だけが目的になってしまいがちです。
でも、どんな仕事にも必ず意味や役割があり、自分がその一部を担っているからこそ、組織全体が動いている、あるいはお客様のために役立っている、という事実があります。
たとえば、単純な入力作業であっても、その先にいる誰かの判断や行動を支えているかもしれません。
お客様への発送作業であれば、ミスのない丁寧な対応が企業の信頼につながります。そう考えると、一見地味な仕事にも「価値」があることに気づけるはずです。
自分の仕事がどう社会とつながっているかを再確認することで、「自分は役に立っている」「この仕事にも意味がある」という意識が生まれ、それがやる気を引き出す第一歩になります。
対処法2:リフレッシュ・休息する時間をつくる
仕事のやる気が出ないときは、無理に気持ちを奮い立たせるよりも、まずはしっかり休む時間を確保することも必要です。
気づかないうちに疲れがたまり、頭も体も限界に近づいていると、どんなに頑張ろうとしても仕事でスイッチが入らずエンジンがかかりません。身体のバランスが崩れかけている、という前兆かもしれません。
これは根性や精神論の問題ではなく、エネルギー切れの状態です。休息をとらずに走り続けていると、やる気が出ないどころか集中力や判断力も落ちていき、ミスや体調不良の原因にもなります。
そのようなときには、例えば、会社の昼休みにスマホから離れて軽く散歩をするだけでも、脳はしっかりリフレッシュできますよね。
また、以下のような小さな「休息」が疲れた心と体を回復させ、自然と前向きな気持ちを取り戻すきっかけになります。
- 週末にしっかり睡眠を取る
- 好きな音楽を聴いて心を緩める
- 仕事とは無関係なことで笑う時間をつくる
意識して回復の時間をとることが、長く安定したモチベーションを保つためには欠かせません。
対処法3:趣味を見つけて没頭する
やる気が出ないときは、仕事から少し距離を置いて、夢中になれる趣味を見つけることが効果的です。好きなことに没頭する時間は、疲れた心をほぐし、リセットするための大切なエネルギー補給になります。
一見、ごくあたりまえのように思えますが、専門領域である心療内科でも、ストレス解消によるメンタルヘルス対策として趣味に取り組むことが推奨されています。
※参考:ココロセラピークリニック心療内科 精神科「メンタルに良い趣味15選!自己実現と充実した人生のヒントが満載!」
※参考:Harvard Medical School「Having a hobby tied to happiness and well-being」
また、仕事とはまったく関係のない活動に熱中することで、「自分には仕事以外にも大切な世界がある」と実感でき気持ちに余裕が生まれます。
心がすり減っているときは、ただ頑張るよりも一度しっかりと好きなことに没頭してみる。それが結果的に、やる気を取り戻すきっかけになるでしょう。
対処法4:ランニングやウォーキングなどの運動をする
仕事でやる気が出ない時は、外に出て体を動かすのもモチベーションを上げるのに効果的。下記の厚生労働省の資料でも、軽いランニングなどの運動はネガティブな気分を発散させる作用があると報告されています。
運動には、ネガティブな気分を発散させたり、こころと体をリラックスさせ、睡眠リズムを整える作用があります。とくに効果的なのは、体の中に空気をたくさん取り入れながら行う有酸素運動。軽いランニングやサイクリング、ダンスなどがそれです。
たとえば、仕事の合間にコンビニへ行くためにほんの数分、外を歩いただけで「気分が少しラクになった」と感じた経験がある人は多いのではないでしょうか。
机に向かったままでは変わらない思考や気持ちも、体を動かすことで自然とほぐれていきます。
無理なトレーニングをする必要はありません。気が向いたタイミングで一駅分歩いて帰る、軽いランニングをするなど、それだけで十分です。
対処法5:直属の上司に相談する
ここまでは、ちょっとしたことで気分転換を促すような、いつでも取り組むことができるような対策をご紹介しました。
ここから先は、もう少し本腰を入れて取り組める対処法のご紹介です。
仕事のやる気が出ないときは、一人で抱え込まずないことが重要です。そこで、上司や信頼できる上長に相談するのもいいでしょう。
職場での悩みや不調は、自分の中だけで考えていると堂々巡りになりがち。特に「このままでいいのか」「誰にも理解されていないのでは」といった思いが強まると、仕事への意欲だけでなく自己肯定感も下がっていきます。
そこで、信頼できる上司や上長に「最近ちょっとやる気が出なくて…」と正直に話してみることで、思わぬ気づきや配慮を得られることがあります。
普段の仕事上のやりとりをとおして気心が通じている上長や上司と、仕事の本題から少し外れた、自分自身のリアルな気持ちを理解してもらうことは、心の疲れを癒してくれる可能性があります。
業務量の調整や配置転換、働き方の見直しなど、より現実的なメリットもありますが、自分自身だけでは変えられない環境などの部分にアプローチしてもらえる可能性もあるのです。
もちろん、上司との信頼関係が前提であり、伝え方には配慮が必要ですが、「困っていることを伝える」という行動そのものが、前に進もうとする姿勢でもあります。
言葉にして相談することで、自分の気持ちや課題が整理され、漠然としていた不調の正体が見えてくることもあります。
そんなときには、後ほどご紹介する、メンターの存在が解決のカギになることもあるでしょう。
上司以外の相談相手を同じ会社の中で見つける
対処法5でご紹介した、上司、上役と相談する機会を持つことは、いろいろな発見につながることをご紹介しました。
しかし、必ずしも上司とそんな信頼関係になれるとは限りませんし、上司だからこそ、相談しにくいというシチュエーションになることもありそうです。
そんなときには、同じ会社の中で、相談できる相手を見つけることも解決法になるでしょう。いわゆる「メンター」という存在です。
メンターには、自身より少し年齢が高く、本音を打ち明けやすいタイプが向いていると言われます。
自分自身の環境や、会社組織の実情に詳しく、余計な説明も要らず、気遣いも不要、でも、自分のことに親身になって相談に乗ってくれる、「兄貴(お姉さん)のような存在」というイメージでしょうか?
このメンターと自分自身をバディ(あるいは、メンティー)という緩やかなコンビを作って、仕事のことはもちろん、ときにプライベートの部分まで相談にのってもらえるという仕組みは、1980年代から、欧米で盛んに取り入れられました。
日本においては、どうしても上下関係という意識が先行する傾向にあったため、なかなか定着しませんでしたが、時代の変化と共に、多くの企業でもオフィシャルな制度として取り入れられるようになりました。
企業によっては、メンターとのフランクな相談時間を正式に勤労時間として認定し、個人の目標設定に取り入れているところもあります。
対処法6:新しいスキルを習得する
仕事のマンネリや評価を得られないことがやる気が出ない原因なら、新しいスキルを学ぶのも効果的な対処法です。
同じ仕事の繰り返しに飽きていたり、成長している実感がないと感じていたりすると、気持ちがだんだんと平坦になっていきます。そんなとき、新しい知識や技術を身につけることは、マンネリを打ち破る強力な方法になります。
たとえば、これまで扱ったことのないツールを使ってみる、資格の勉強を始める、オンライン講座で基礎から学び直してみるなどです。
ほんの少しの「新しいこと」が日々の業務に新鮮な視点をもたらし、自分の可能性を広げるきっかけにもなります。
そのようなスキルはそう簡単に身に付かない、と考えてしまうこともあるでしょう。
しかし普段から、あの資格を持っていたら素晴らしいとか、いつかはチャレンジしてみたい、と心の奥深くにしまっていた目標はありませんか?
モチベーションが下がりがちな今こそ、新しい挑戦を始めるチャンスかもしれません。そんなチャンスは、きっと心のエネルギーを満たしてくれるでしょう。
「学ぶ」という行動には、自分自身を、自分の手で変えられるという手応えを得られます。
たとえ業務内容そのものがすぐに変わらなくても、スキルを身につけているという事実が、自信となって前向きな気持ちになるはずです。
対処法7:キャリアプランを明確にして目標を立てる
なかなかやる気が出ないときは、今の自分がどこに向かって働いているのかを、はっきりさせることで気持ちが前に進みやすくなることもあります。
自身のキャリアプランが曖昧なまま、漫然と仕事に向かっていると、目の前の仕事が「ただこなすだけの作業」になってしまい、日々の積み重ねに意味を見出せなくなることがあります。
でも、「○年後にはこんな仕事をしていたい」「(いつかは)このスキルを身につけたい」といった目標があると、その道の途中にある仕事にも目的が生まれます。
たとえば、今は雑務と感じられてやりがいを感じられないとしても、「ここで得た経験が、将来マネジメントに活きる」「次の転職で活かせる」と思えるだけで取り組む姿勢は大きく変わります。
未来の自分が後悔しないかどうかを基準にすると、同じ仕事でも意味合いがまったく違って見えるでしょう。
迷いや不安があっても「自分は何のために働いているのか」を思い出せれば、やる気が出ない日でもまた前に進めるようになります。

最近では、よりメンターとの相談やりとりを充実させるため、メンターの選び方について社内の人間関係が影響しないよう、会社側が口出しせず、自由に社内マッチングできる、といった仕組みを導入している企業もあります。やはり、中期的なキャリアについて目標が見えにくくなるときなど、心を打ち明けられる存在が大きい役割を果たす、ということに気づいたからではないでしょうか?
仕事でやる気が出ない・モチベーションが低い時のNG行動
仕事のやる気が出ないときこそ、そのときの思いつきで動いたり、重要な判断をしたり、まして生活を乱したりすると、状況はさらに悪化しやすいので注意が必要です。
仕事に対するやる気が出ない・モチベーションが上がらない時に絶対に避けたいNG行動が次の通りです。
- (とりあえず)転職する
- 仕事に対して適当に取り組む
- 不規則な生活を送る
まず、「(とりあえず)転職する」という行動は、周囲の環境が変わるだけで根本的な原因の改善にはつながりにくい、ということを理解しておきましょう。
そして冷静に現実を分析したうえで、転職する意義を明確にすることが大切です。
現実から逃避することを目的とせず、転職によって実現したい、具体的な目標、目的を、じっくりと考えていくことが重要です。
次に、やる気が出ないからといって「仕事に(本気にならず)適当に取り組む」と、当然、組織から期待されている成果が出ないことにつながり、そんな自分自身に対する自己嫌悪や周囲からの評価ダウンにつながり、さらに気持ちが沈んでいく悪循環に陥ります。
頑張れないときこそ、最低限やるべきことだけは丁寧にこなすことで、自分への信頼を失うことなく、自分のリズムを守ることができます。
そして意外に見落とされがちなのが「不規則な生活」。睡眠不足や食生活の乱れは、集中力や気分の安定に影響します。
一時的な不調の中での衝動的な行動や乱れた生活は、状況をこじらせるだけになります。だからこそ、焦らず、冷静に気持ちを立て直す対策が大切です。

転職が当たり前になった現代ですが、人生において大きな決断の機会であることには変わりがないでしょう。キャリアカウンセリングの現場でも、「転職の理由がネガティブなままだと、転職先で再現してしまう懸念がありますよ」と率直にお伝えすることがあります。ポジティブな目標があるからこそ、転職先でも、嫌なことがあっても、またがんばろうという意欲、気力が生まれてくるのではないでしょうか?
慢性的に仕事でやる気が出ないのは「うつ病」などの病気の可能性も
- 朝ベッドから起きるのがつらい
- 仕事のパフォーマンスが落ちる
- 毎日が充実せず、後ろ向きなイメージばかり想像してしまう
このような状態が一時的なものではなく、”長期間続く場合”はうつ病、抑うつ状態などの精神疾患の可能性があります。
※参考:品川メンタルクリニック「「やる気が出ない」「全部めんどくさい」のは怠けではなく『うつ病』のせいかも?」
うつ病や抑うつ状態とは、単なる気分の浮き沈みとは違い、脳の機能が一時的にうまく働かない状態で、脳内物質が正常に分泌されない状態のため、「気合い」や「努力」では乗り越えることが難しく、専門的な治療を要する場合もあります。
また、本人が「これは(自分自身の)甘えかもしれない」と考えてしまうことも少なくありませんが、まじめで責任感の強い人ほど知らず知らずのうちに限界を超えてしまうケースが多くあります。
そのため、「最近ずっとおかしいな」と思ったときは、自分を責めるのではなく、まず体と心の状態を確かめることが必要です。
やる気が戻らない日々が続いているなら、それは「休むタイミング」を知らせるサインかもしれません。
「仕事が続かないのはメンタルが弱いせいかもしれない」と感じている方は少なくありません。ですが、実際には「自分に合わない働き方」が原因になっていることも多くあります。この記事では、メンタルが弱いと感じやすい人の特徴や働きづらさの原因を[…]
慢性的に仕事でやる気が出ないときの3つの対処法
医療機関を受診する
前述したように、仕事のやる気が出ない・だるい日が続く場合はうつ病の可能性があるので、まずは心療内科、メンタルクリニックを受診しましょう。
うつ病は、単なる気分の落ち込みではなく、脳の働きに変化が起きる“病気”。そのため、本人の意志や努力だけで立て直すのは難しく、専門的な診断とケアが必要になります。
「朝起きるのがつらい」「仕事のパフォーマンスが明らかに落ちた」「何をしても充実感がない」といった症状が何週間も続いているなら、それはすでに体からの“休んでほしい”というサインかもしれません。
心療内科、メンタルクリニックでは、医師が症状の経過や生活状況を丁寧に聞き取り、必要に応じて適した薬やカウンセリングなどの治療方針を立ててくれます。
職場への配慮が必要なケースもあり、診断書の発行や復職に向けたサポートを受けられる場合もあります。
心の不調は早期発見・早期対応が大切。ほんの少しでも「今までと違う」と感じたなら専門機関に相談することをためらわないでください。

現在は、優れた薬も開発され、処方により短期間で快復することができるようになっています。 国としても、メンタルヘルス対策を重視して法的な制度も整え、労働者の保護を推進しています。
仕事を休む
仕事のやる気が出ない状態が続いているときは、思い切って仕事を休むことも必要です。
無理をして働き続けることで心や体の不調が悪化すれば、回復までにもっと時間がかかってしまいます。
うつ病、抑うつ状態などの精神疾患と診断された場合は、医師に相談することでその症状にあわせて「休職診断書」を出してもらうことができます。
この診断書を会社に提出すれば制度に沿って正式に仕事を休むことができ、焦らず治療に専念することができます。
休職中も、条件を満たせば傷病手当金などのサポートを受けられる場合があり、経済的な不安を減らすことも可能です。
働けないほどつらいと感じるときは、焦らず、頑張りすぎず、思い切って一度休む決断をすることが、未来の自分を守る行動にもつながります。

現代では、一見好調そうに見える方でも、心の不調を抱えている事例が多いことがわかってきており、誰でも、自身でも気づかないうちに不調をきたしている可能性があります。一人で悩まずに、小さな身体の変化であっても見逃さないことが肝要です。
転職を検討する
心身に不調があり、仮に休職したとしても会社の環境や待遇が明らかに変わらないのであれば、転職を検討する機会になるかもしれません。
やる気が出ない原因が、仕事内容や人間関係、評価制度、職場の雰囲気など“職場そのもの”にある場合、あるいは、職場そのものがいわゆるブラックな環境であった場合など、どれだけ自分が努力しても根本的な改善は難しいことがあります。
たとえば、上司の対応が一貫して(不当に)冷たい、働き方に柔軟性がなく改善される見込みがない、努力して明らかな成果を出してもまったく評価されず、評価に対して適切なフィードバックもない。
そんな劣悪な環境で復職しても、同じストレスに再びさらされてしまえば、再びストレスが蓄積してやる気が出ない状況を繰り返すだけになる可能性があります。
転職は決して逃げではありません。むしろ、無理なく続けられるためにはどんな環境が適しているのかを見直すチャンスです。
今の場所で「もう頑張れない」「新たな目標を目指したい」と感じているなら、新しい職場で新しい一歩を踏み出すことも自分を守るための前向きな決断です。
職場に復帰するか、転職に踏み出すかを考えるときは、「この会社で、自分は安心して働き続けられるか?」という視点を持つことが大切です。

職場から離れることに対して、(特に)責任感の強い方は罪悪感を抱きがちです。それゆえ、復職が義務であるかのように考えてしまうこともあるでしょう、しかし職場環境が何も改善されていないのであれば、復職すること自体を慎重に検討する必要もありそうです。
「仕事に対して不満があるけど、これは辞めどき?」と迷っている方のために、仕事の辞めどきがわかるサインについて解説。社内環境や待遇面はもちろん、体調面も仕事を辞めるかどうかを判断する基準となります。記事の後半では、「仕事を辞める前に確[…]
転職活動では「平日に面接を行う」のが基本。しかし、在職中の方だと「平日は休めない」という人が多いでしょう。そこで今回は、在職中の転職活動で平日に休めないときの対処法について解説。平日に休みを取得する方法だけでなく、面接の日程を業務時[…]
まとめ
仕事でやる気が出ないと感じるのは、誰にでも起こり得る自然なことです。
原因を見つめ直してみると、「仕事内容にやりがいを感じられない」「人間関係がストレスになっている」「努力が正当に評価されていない」など、負の感情を起こす様々な要因を抱えながら、心のどこかで無理に頑張ろうとしている自分に気づくかもしれません。
まずは、自分の気持ちを整理し、できることから少しずつ対処していくことが大切です。
趣味を楽しむ、運動をする、信頼できる人に相談するなど、小さな変化がやる気を引き出すきっかけになります。
それでも改善しない状態が長く続く場合は、うつ病などの可能性も視野に入れ、心療内科の受診や、必要に応じて休職も検討してみてください。
もし休んでも職場の環境や条件に変わる見込みがないようなら、転職という選択も決して間違いではありません。無理をせず、自分の心と体を大切にしながらよりよい働き方を見つけていきましょう。
転職UPPP編集部は、IT・Web業界に精通した起業家、マーケティングのプロフェッショナル、そして豊富な転職経験を持つライター・ディレクターが集結した専門チームです。起業や独立、法人営業、Webマーケティング、メディア運営など、それぞれのキャリアで培った知見を活かし、転職市場の動向を分析しながら、実体験に基づいた信頼性の高い情報を発信しています。転職の成功と失敗をリアルに経験したメンバーが、読者にとって本当に役立つコンテンツを提供します。
運営会社情報
- 運営会社:UPPGO株式会社
- 所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル5F
- 有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-313755
- プライバシーマーク登録番号:第21004733(03)号
- お問い合わせ:contact@tenshoku-uppp.com